「遺言」のこと、ないしょで教えて。
1,そもそも「遺言」ってなに?
お客様が亡くなったあと、お客様自身の「財産」や「権利関係」をどうして欲しいか?
また伝えたい方に想いを「法」の規定に沿って記しておく文書のことです。
(法の規定通りの文面であればOK。使用する紙質や種類は特に問題になりません。
ただ容易に消えてしまう鉛筆やフリクションペンで書くのは避けて下さい。
また、自筆証書遺言の印鑑は実印でなくてもOKです。)
(公正証書遺言は実印が必要)
※終活の時に用いられる「エンディングノート」に死後の「財産」「権利関係」について書いても有効にはならないので注意です。
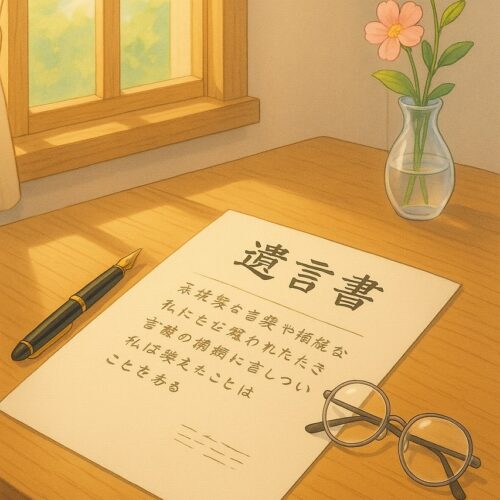
もし、遺言を書かなかった場合や、遺言が「無効」となった場合は、法律に定められいるルールに従って配偶者・子供・親・兄弟等の「相続人」が「相続」することになります。
また、残された財産をどのように分けるのかは、相続人で話し合いによって決めることに
なります。(相続の際にでてくる「遺産分割協議」のことです)
2,遺言を「書いておいたほうがいい」人
実は・・・皆さん書いておかれたほうがいいのですが、こんな方は特に書かれておくことを強くお勧めします。
- (特に未成年の)子供がおられる方
- 再婚されている方や、前の配偶者の方との間に子供がおられる方
- 「おひとりさま」「おふたりさま」
- 内縁関係・同性パートナーがおられる方
- 特定の方や、特定の団体に渡したい方
- 事業経営をされている方
- 不動産をお持ちの方
- 親子・親族関係がよくない方 など。

特に、「おひとりさま」「おふたりさま」で介護等で世話になった方(例 甥・姪や息子の嫁、献身的に対応してくれた友人・知人など)へ遺したい、入籍せずに一緒に暮らしてきた
パートナーに残したいなど、特別な事情で「相続人」以外の方に渡したい場合は、必ず(公正
証書にして)書いておくようにしましょう。
また、全財産は「残された配偶者」に、この不動産は「あの息子」に、この預貯金は「この娘」になど、特定財産を特定の相続人に渡したいや、法定の配分を超えて(または減らして)渡したい場合等も必ず書いておくようにしましょう。
3、書くのが「面倒」・・その時は
まず、「遺言」には大きく分けて3つの方法があります。
1,自筆証書遺言
遺言者が手書きで作成
2,公正証書遺言
遺言者が公証役場に出向き公証人が作成。
3,秘密証書遺言
遺言者が作成し封印したものを公証人役場に持参し、遺言が入っていることを公正証書で認証
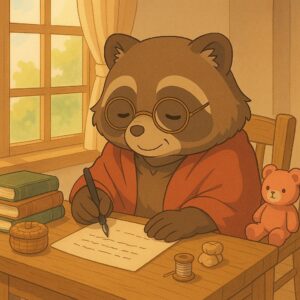
それぞれにメリット・デメリットがありますが、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は遺言者で作成しなければなりません。また保管については遺言者本人で行います。また、死後、遺言が発見された場合は、家庭裁判所による「検認」が必要です。
これら2つは遺言に不備があった場合「無効」になる可能性がおおいにあり、また紛失・発見できない、という危険性があります。
※なお、自筆証書遺言は紛失・改ざん等の問題を解消するために、法務局で遺言を預かるという「自筆証書遺言書保管制度」があります。
これに対し、公正証書遺言は、3つの中では一番費用がかかるものの、事前に打ち合わせした内容を公証人と証人2名の前で「口述」して作成します。また作成された原本は公証人・証人・遺言者で署名して、公証役場で保管。そのため信頼性が高く、また紛失・改ざんの恐れがもっとも低い遺言です。
お客様ご自身で公証役場に予約し、公証人の方と打合せ・作成することも可能ですし、また一連の煩わしい手続きを、最初からすべて「行政書士」にお任せ頂くこともできます。ぜひご相談下さい。
4,「付言」はお客様からの最後の「メッセージ」
遺言書には、「本文」に添えてお客様の思いや気持ち、なぜ、この遺言内容を書くことになったのか?などの文章を書くことができます。これを「付言(付言事項)」と言います。
「付言」そのものは、残念ながら法的効力を持たないので、必ずしも書いたことが実行されるかどうかの確実性はないものの、残された家族の理解と納得を促すには非常に効果的です。またお客様からの家族の方々への感謝の意を伝える最後の場ともいえるでしょう。
特に、相続人以外の方に遺産を渡す場合や、特定の方に多く遺産を渡すなどの場合、その理由や思いを記しておかれると争いなく相続されることが期待できます。
どの遺言方式でも「付言」は添えることができます。ただ、あまり長くなりすぎてもどうかと思いますので、できるだけ簡潔にまとめるようにしましょう。

 1000-×1000px jpg-e1744034025457.webp)